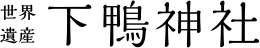年間祭典一覧表
春の神事
- 2月3日
- 節分祭、追儺弓神事、追儺豆まき、御真木神事、古神符焼納神事
- 2月初午の日
- 初午祭 (末社のまつり)
- 2月11日
- 紀元祭
- 2月17日
- 祈年祭(土解祭)
- 2月22日
- 御内儀御祈祷祭
- 2月23日
- 天長祭
- 3月3日
- 流し雛
- 3月7日
- 三井社祭 (摂社のまつり)
- 4月1日
- 雑太社祭 (末社のまつり)
- 4月14日
- 日吉社祭 (摂社のまつり)
葵祭の神事
- 5月3日
- 流鏑馬神事
- 5月5日
- 歩射神事、少年剣道、なぎなた、詩吟奉納
- 立夏の日
- 更衣祭
- 5月
- 献花祭
- 5月
- 献茶祭
- 5月12日
- 御蔭祭
- 5月14日
- 堅田供御人鮒奉献祭
- 5月15日
- 賀茂祭(葵祭)
- 5月
- 煎茶献茶祭
秋の神事
- 9月9日
- 結納祭→令和4年中止
- 9月
- 印章祈願祭
- 中秋の名月
- 名月管絃祭
- 10月14日
- 出雲井於社祭 (摂社のまつり)
- 10月17日
- 神嘗祭
- 10月23日
- 霜降祭 (摂社のまつり)
- 10月15日
- えと祈願祭(崇敬者大祭)
冬の神事
- 立冬の日
- 更衣祭
- 11月3日
- 明治祭
- 11月15日
- 七五三詣 河合社祭 (摂社のまつり)
- 11月23日
- 新嘗祭
- 11月下旬
- 比良木社 お火焚祭 (摂社のまつり)
- 12月12日
- 御薬酒、若水神事
- 12月13日
- 相生社祭(縁結び祭)
- 12月31日
- 除夜祭、大祓式
月次の神事
- 毎月1日
- 月次祭
蹴鞠はじめ

毎年1月4日の日、古くから御所に伝わる京の伝統行事「蹴鞠」が奉納され、一般に公開される。水干、袴、烏帽子姿の鞠人が、大勢の人垣が取り囲んで見守る中、皮製の沓(くつ)で鞠を蹴り上げていく。鞠は鹿革を使用し、地面に落とさないよう巧みな足さばきで蹴り上げて渡していく様は、競技のようでありながら、作法を重んじた儀式的な芸能の様子を呈している。
蹴鞠は、現在では古典伝統芸能として尊ばれており、京都では蹴鞠保存会によって折節に蹴鞠が催され、伝統が継承され続けている。境内の鞠の庭には、15メートル四方の隅々に松、桜、柳、楓を植え、これを懸り(切立)としている。 鞠人たちは、4人、6人、8人1組で輪となり、沓の背で鞠を蹴り上げ、巧みな足さばきを競い合う。鞠を蹴り上げる乾いた音と鞠人たちのかけ声は、その瞬間、時代を忘れてしまうような不思議な世界に見ている人を誘い込む。
蹴鞠は、およそ1400年前に中国から仏教などと共に伝わった。その後、中国や東南アジアでは衰えてしまったが、日本では独自に発展してきた。天皇から民衆に至るまで、老若男女の差別無く広くたのしまれたものである。
明治維新になって西欧の様式に移行されるに従い、日本の古来の習俗は廃絶の一途を辿って行った。そこで、明治天皇によって蹴鞠を保存する旨御下命があり、明治36年に蹴鞠保存会が創立され、現在に至っている。
成人祭

下鴨神社では、成人の日に新しく大人の仲間入りをする男女が平安装束をつけて本殿にて成人としての誓いを新たにしていただきます。将来、神社と深い結びつき(氏子意識、婚礼を含む人生儀礼)をもって頂く事を目的とした。今年の成人祭、これからも新成人になられる方々の思い出作りのサポートを心がけて行く所存です。
御粥祭(御戸開神事)

野菜果物とともに小豆粥と大豆粥をお供えし、五穀豊穣、国家国民の安泰を祈願します。小正月と呼ぶこの日に小豆粥で祝い、邪気を払います。御粥の中に、それぞれ柔らかく煮いた小豆、餅を入れた小豆粥、大豆粥を神前に供し、先着順で一般の方にも接待(志納)が行われます。
節分祭 2月3日

朝より本殿前で節分祭、引き続き古神符焼納神事。舞殿にて追儺弓神事が行なわれ、午後から追儺豆まきの後、御眞神事が行われる。雨天決行。
| 午前10時頃 | 節分祭 |
|---|---|
| 午前10時半頃 | 比良本社節分祭 |
| 午前11時頃 | 古神礼焼納式 |
| 正午頃 | 追儺弓神事 |
| 午後1時頃 | 福豆・福餅撒き |
| 午後1時半頃 | 御眞神事 |
朝より本殿前で節分祭、引き続き古神符焼納神事。舞殿にて追儺弓神事が行なわれ、午後から追灘豆まきの後、御眞神事が行われる。雨天決行。
流し雛 3月3日

さんだわらに乗せたひな人形をみたらし川に流し、子供たちの無病息災を祈る神事。甘酒の接待などもある。 雛まつりは、もともとケガレを雛に託して祓う神事であるが、現在では雛壇に飾って祝うのが一般的となった。地方によっては、今でも雛を川に流す風習が残っている。 雛壇に飾られる雛は衣装などもきらびやかで凝った細工が施されているが、流し雛はきわめて簡素なものが用いられる。多くは、色紙などを使って作った男女二人の雛が用いられている。
流鏑馬神事 5月3日

流鏑馬は「やぶさめ」、あるいは「やぼさめ」と読みます。また「矢伏射馬」とも書きます。『貞丈雅記』に「やぶせむまの略語なり」とあるように、馬を走らせながら鏑矢(かぶらや)を射ることである。当神社では、流鏑馬とは云わずに「騎射」(きしゃ)と明治初年まで呼んでいた。この騎射が、いわゆる流鏑馬の原形です。その騎射の歴史は『日本書紀』雄略天皇即位の年(四五七)に「騁射」(うまゆみ)をおこなった、とある。また天武天皇九年(六八二)、「長柄宮(ながらのみや)にて馬的射(むなもと)」ともあり、これもまた流鏑馬のことですから、古くから行われていたとわかる。当神社では、境内の糺の森から古墳時代の馬具が出土しました。また、『続日本紀』に「文武天皇二年(六九八)賀茂祭(葵祭)の日に民衆を集めて騎射を禁ず」とあり、葵祭の日の騎射に大勢の見物人が集まるため三度も禁止令が出るほど有名になっていたことからも、古くから行われていたことがうかがい知れます。後鳥羽上皇が、当神社へ御幸され、糺の森の馬場で「やぶさめをごらん」(『百錬抄』)になりました。この頃から騎射を流鏑馬と呼ばれるようになりましたが、葵祭の前儀流鏑馬神事は、儀式の最初の三馳を伝統によって騎射(きしゃ)と称し、作法や装束、用具などは古来からの法式によって近衛府(このえのつかさ)の大将が長官となり、近衛府の将監(じょう)や将曹(さかん)、馬寮(めりょう)の助や允(じょう)、あるいは当神社の氏人が騎射を行います。その後で武家が狩装束を着け、流鏑馬を行うのが習となっています。文亀二年(一五〇二)、葵祭の路頭の儀が中絶したことによって騎射もまた中絶しました。神事は中断しましたが、武家は各地で流鏑馬として盛んに行うようになり、様々な流儀や作法が派生しました。元禄七年(一六九四)、葵祭が再興されたとき、騎射も伝統の作法により再興されました。ところが、明治二年(一八六九)東京遷都祈願行幸のときに行われた後、ふたたび中絶するに至りました。去る、昭和四十八年、下鴨神社式年遷宮の記念行事として、名称を流鏑馬神事と改め、百数年ぶりに復興しました。これを期に、騎射の伝統を受け継いだ公卿の流鏑馬の保存を図るため、糺の森流鏑馬神事等保存会を結成し、小笠原弓馬術礼法宗家小笠原清忠氏をはじめ、小笠原流同門会のご支援によって毎年五月三日に、葵祭の前儀、流鏑馬神事として騎射が行われています。流鏑馬神事、走馬の儀は、(公財)京都市文化観光資源保護財団、(公財)馬事文化財団、(公財)糺の森財団、京都府の助成により実施、斎行されています。
斎王代禊の儀 5月4日

葵祭の斎王代(さいおうだい)以下、女人列に参加する四十人の女性が身を清める神事。毎年、上賀茂神社と当神社の交代で行われる。 斎王とは、平安朝時代未婚の内親王が選ばれて奉仕した。現在は代理として、京都在住の一般の方から選ばれた女性が務めている。十二単を着て神社のみたらしの池で川の水に手を浸し、身を清める御禊(みそぎ)を行う。 古くは鴨川の河原で行われてたが、鎌倉前期に斎院の廃止と共に中断。昭和三十一年の斎王列復活により、両社の隔年交替で行うこととなった。日時は一定しないが五月初旬、御手洗川のほとりで、葵祭に先立ち斎王代と女人列が清流に臨んでハライを受ける。 青葉こもる神域で華やかな十二単の上に白い小忌衣(おみごろも)を召された斎王代、あどけない童女、小袿の命婦(みょうぶ)・女嬬(にょじゅう)・内侍(ないし)・女別当など五十余名の女人列が雅楽の流れる中、進む様はまことに優美な王朝絵巻である。 この禊の儀をおえると、いよいよ葵祭は間近い。
歩射神事 5月5日

弓矢を使って葵祭の沿道を清める魔除けの神事。 歩射神事は、3日に同神社で行われる馬上の流鏑馬に対して、地上で矢を射ることに由来しており、平安時代に宮中で行われていた「射礼(じゃらい)の儀」が始まりと伝えられている。 射手が弓を鳴らす「蟇目式(ひきめしき)」で四方の邪気を祓い、鏑矢を楼門の屋根を越えて飛ばす「屋越式(やごししき)」、大きな的を射る「大的式(おおまとしき)」、連続で矢を射る「百々手式(ももてしき)」がそれぞれ行われる。また、この四式をもって「鳴弦蟇目神事(めいげんひきめしんじ)」と呼ばれ、賀茂祭(葵祭)の安全祈願とされている。
古武道奉納 5月4日

5月4日、下鴨神社では午前中の献香祭につづいて、午後には一転して静寂から豪気へ、勇ましい古武道が奉納される。関東から沖縄まで外国人も交えた十二余流派が参集、日頃の研鑽の成果が披露される。薙刀、剣術、柔術、居合をはじめ珍しい棒術や鎖鎌などの古武道を直接拝見できる貴重な機会でもある。
献花祭 5月中旬

貞松斎米一馬いらいのゆかしい手振を伝える遠州宗家一門が、精魂こめて生花(木もの)を生け、当神社の神前に供える。門弟の人々も参列して年に一度、鴨の大神を慰める前儀。
献茶祭 5月中旬

葵祭を祝い、神の御心を和める神わいの行事として献茶祭が行われる。表、裏、武者小路の三千家家元が交替で奉仕。当日は祝詞奏上の後、舞殿において家元の点前で濃茶と薄茶が点てられ、神前に奉献される。副席や野点席、点心席なども設けられ、境内は和服姿の人々で華やかな雰囲気である。
御蔭祭 5月12日

比叡山山麓の八瀬御蔭山より神霊を本社へ迎える神事。 明治初年の神社祭祀法制化以前の年中行事を旧祭式、以降を新祭式と称して区別している。 現在の御蔭祭(みかげまつり)は、旧祭式のころは御生神事(みあれしんじ)と呼ばれていたが、新祭式となって、神事斎行の場所が東山三十六峰の2番目の山、洛北上高野の御蔭山の麓であったことからその名となった。 旧祭式時代の御生神事は、旧暦4月の午の日。早朝より禮殿(らいでん)における解除(げじょ)の樹下神事(じゅげしんじ)から始まる。本宮を進発するときの歓盃(かんぱい)の儀。そうして神領内行粧を整える檜垣(ひがき)。御蔭山の山麓の禁足地へ行粧が到着すると、高野川に面した船繋ぎ岩(磐座(いわくら))において御生神事が行われる。御蔭山の麓を風俗歌を奏しながら巡る神おろしの神事。その後、神領内総社神前での路次祭(ろじさい)。糺の森に達してから芝挿神事(しばさしのしんじ)。切芝神事(きりしばのしんじ)。御生ひきと称して御綱を正官がひく、本宮の儀の全てを総称して、御生神事と呼ばれてきた。 古代から、鴨氏が伝えてきた思想信仰を基とする祭祀と氏祖神の祭を御蔭祭と呼ぶようになり、氏子の祭へと変貌した。また、上知令後、神領内の各総社が独立したため諸神事が略されたことなど、大きな変革がもたらされた。しかし、古代から森林を祭祀場とする切芝神事は、御生された御神霊を神馬の背に移御し、御神前で御祭神のご来歴、風俗歌三代詠(さんだいえ)を奏上するのと、忌子(童形)御杖を奉持、先導する本宮の儀は、今は葵祭にさきがけて5月12日に行われている。 この祭は我が国最古の神幸列として、毎年神馬に神霊を遷し本社に迎える古代の信仰形態を今に伝える祭として有名である。また、御蔭祭の日の午後4時頃、本社に於て切芝遷立の儀の時の舞を「東游(あづまあそび)」という。
賀茂祭(葵祭) 5月15日

今から約一四〇〇年前の(540~572)年、凶作に見舞われ飢餓疫病が蔓延した時に、欽明天皇が勅使を遣わされ、「鴨の神」の祭礼を行ったのが起源とされている。上賀茂、下鴨両神社の例祭であり、この国の祭り中の祭として「枕草子」にも称えられている。また、「祇園祭」「時代祭」と並んで「京都三大祭」の一つに数えられるが、時代祭は町衆参加の町の人が主体となる祭りであるのに対し、葵祭は官の祭であったことが色濃く残されている。 応仁の乱の後、元禄六年(一六九三)までの約二〇〇年の間、また、明治四年(一八七一)から明治一六年(一八八三)、昭和一八年(一九四三)から昭和二七年(一九五二)までの間は、祭の中断や行列の中止があった。 葵祭は平安王朝時代の古式のままに「宮中の儀」「路頭の儀」「社頭の儀」の三つに分けて行われ、内裏神殿の御簾をはじめ、御所車、勅使、供奉者の衣冠、牛馬にいたるまで、全てを葵の葉で飾ったことから「葵祭」と呼ばれるようになった。「路頭の儀」と「社頭の儀」がよく知られており、路頭の儀が葵祭のハイライト、都大路の行列である。 行列は、勅使をはじめ検非違使、内蔵使、山城使、牛車、風流傘、斎王代など平安貴族そのままの姿で列をつくり、午前十時三〇分、京都御所を出発する。そして、王朝風の優雅な列が市中を練り、下鴨神社を経て上賀茂神社へと向かう。
煎茶献茶祭 5月中旬

葵祭を締めくくる行事で、神に煎茶(せんちゃ)を奉納する。 神前でカツラの枝とアオイの葉を烏帽子(えぼし)に飾った神官によるお祓い、お供え、祝詞が行われ、引き続き、舞殿で白の紋付きに水色の袴姿の小川流家元が白磁、白泥の道具を使って厳かに一煎を入れ、東と西の両御祭神に献じる。 境内では、煎茶席と玉露席が設けられ、列席者の方々には煎茶が接待される。
蛍火の茶会 6月上旬

糺の森に蛍が飛び交う、初夏の夕暮れの六月初旬に雅な恒例行事である「蛍火の茶会」が開催される。 楼門前には「糺の森納涼市」として京の老舗が午後一時より開店し、処狭しと軒を並べながら二十店舗余りが出店され、また、午後五時より中門前において奉告祭が斎行されると同時に橋殿・細殿(共に重要文化財)にて茶席も開筵される。午後六時頃には神服殿(重要文化財)において十二単の着付けと王朝舞や箏曲の演奏がおこなわれ、訪れた参加者は、初夏の夜空に蛍火が舞う幻想的な雰囲気に酔いしれる。※お茶席には申し込みが必要ですが、その他の催事にはご自由に参加いただけます。 【茶会について】下鴨神社とお茶は、古くから関係が深く、寛正年間(一四六〇年頃)以来、内裏の御門前に桧垣茶屋を開き、参内の公卿にお茶を供したり、行幸、御幸等の行粧に供奉し御休憩所で御茶を献上するなど茶の座を有し、江戸時代には、「担い茶屋」と称して都の風雅とはやされていました。 桧垣茶屋は、下鴨神社の社職で西村姓の家が代々つぎ、糺の森の泉川のほとりに茶所を構えていたのが謂ば本店でありました。 下鴨神社には、神官二十二家と氏人一九〇家による社職三十六職があり総勢三四〇家によって成り立っていました。 代々の桧垣茶屋西村与市は、同家系が氏祖社と仰ぐ比良木神社(摂社、出雲井於神社)の神前に茶の木を育てその葉を摘んで年中祭事に御茶を捧げる役を勤める社職でありました。いまなお、比良木神社の社前には何代目かの茶の木を見ることができます。 年中の祭事の日には、参拝の人々にもお茶がふるまわれ、明治二十九年(一八九六)、アメリカの画家セオドア・ウォレスは、その風情を描いています。御手洗川で催されている納涼茶席の情景です。 この時代はまだまだ糺の森の自然は豊かでした。土地の古老は、梅雨時に糺の森に涼みに出るとほほに痛いほど飛ぶ蛍があたってきたと話しています。ウォレスの描いた茶会の時代からやがて下鴨神社は、国が管理する神社となって市民の行事はほとんど廃絶しました。 糺の森も、昭和二十年代に樹間の清流は枯渇し、唯一流れを留める泉川さえ農薬に汚染され蛍は根絶し多くの昆虫も絶滅寸前となってしまいました。 そこで、地元の農会や氏子の方々の協力で泉川流域の清掃を繰り返し、蛍の幼虫を放ったところ糺の森のあちらこちらに蛍火の飛び交うのが見られるようになり、平成三年より約一〇〇年ぶりに蛍火の茶会として再顕することとなりました。 【納涼市について】江戸時代から、京の夏の避暑地として下鴨神社の糺の森を流れる川の辺に茶店が建ち並び、庶民の納涼場として船を浮かべた茶会のほか能(糺能)や相撲の催しがありました。しかし、明治時代になると下鴨神社は国が管理する神社となり、庶民の行事も次第に廃絶し、納涼市の姿も消えていきました。この度、およそ百年ぶりになつかしい風情として「糺の森納涼市」を再現いたしました。当時の様子を描いた歌川広重の「糺川原夕立」は、あまりにも有名な作品です。
みたらし祭 土用の丑の日 (前後10日間)

平安期の頃、季節の変わり目に貴族は禊祓いをして、罪、けがれを祓っていた。土用の丑の日に御手洗池の中に足をひたせば、罪、けがれを祓い、疫病、安産にも効き目があるといわれている。毎年、土用の丑の日に境内御手洗池に祀られている御手洗社において「足つけ神事」が行われる。老若男女が集まり、御手洗池で膝までを浸し、無病息災を祈る。
夏越神事(矢取神事) 立秋前夜

一年の厄を払い、無病息災を祈る神事。 御手洗池に斎竹(いみだけ)を立てて清め、中央に斎矢(いみや)を立て、奉納された厄除けの人形が流されると、裸になった氏子男子が一斉に飛び込み、矢を奪い合う。これは、当神社の御祭神玉依媛命が川遊びをしていると一本の矢が流れ着き、持ち帰ったところ懐妊し、賀茂別雷神を生んだという故事にちなみ、矢取神事とも呼ばれる。
名月管絃祭 中秋の名月の日

昭和38年から一般に公開された管絃祭は、平安時代以来の伝統を持っている。ススキの穂を飾り、かがり火がたかれた舞台では、壮重な雅楽にのって舞楽が演じられる。 祭典は午後5時半から橋殿で行われる。神事の後、古式ゆかしい舞楽や十二単(ひとえ)の平安貴族舞などが2時間にわたって奉納される。斎庭に設けられた観月茶席で名月を楽しむ。
えと祈願祭(崇敬者大祭) 10月第3日曜日

毎月9日は大国さまのお祭りの日です。大国さまは出雲神話の「因幡の白兎」のお話で有名な神様ですが、この神様は数多くのお名前を持っておられることでも知られています。昔の人々は神様のお力を四つ(四魂)に分けて考え、勇猛な魂の働きを荒魂、柔和な魂の働きを和魂、不思議な働きをする魂を奇魂、幸福をもたらす働きをする魂を幸魂と称しました。それゆえ一人の人格の神様でも四魂の別によって名前を異にする場合もあり、下鴨神社の言社とよばれる7つのお社は大物主神と称する場合は和魂の現れ、八千矛神と称する場合は荒魂の現れとなるなどそれぞれ異なったお名前の大国さまをおまつりしています。それぞれの神さまは干支の守り神としても有名で、下鴨神社の干支詣りとして古来からの信仰を集めていました。えと祈願祭(崇敬者大祭)は豊かな秋の稔りを感謝する年に一度のお祭りで模擬店や福引き、舞楽の奉納など境内は終日多くの参拝者で賑わいます。 言社では、大国主命を各々言霊の働きによって七つのお社に分け、特に本社の大前にお祀りされた、いわゆる下鴨の繁昌大国神である。 福徳円満、長寿、殖産興業の御神徳を発せられ、その御神像は、菊花と二葉葵の飾り金具を取り付けた五合桝を神殿とし、その中にお祀りして授与されるところから『半升』は『繁昌』なりとして多くの崇敬者から深く信仰されている。
明治祭 11月3日

11月3日は現在では文化の日となっていますが戦前は明治節、明治時代は天長節と呼ばれ明治天皇の御誕生になられた日として祝日になっていました。明治天皇は御名を睦仁(むつひと)御称号を祐宮(さちのみや)と称せられ孝明天皇の第2皇子として御降誕になられました。この日、東京の明治神宮には天皇陛下よりの勅使が遣わされ明治天皇の御誕辰を言祝ぐ祭典が行われ、また明治天皇を祀る伏見桃山陵は終日多くの参拝者で賑わいます。近代日本の礎を築かれた明治天皇の御偉業を称え、その御威徳を景仰するとともに明治の御代を追慕する趣旨から、昭和2年に制定されました。ここに改めて明治の御代を偲び、明治天皇の御聖徳に思いを巡らせたいものです。 明治節 亜細亜の東 日出ずる処 聖の君の現れまして 古き天地 閉ざせる霧を大御光に 隅なく払い 教えあまねく 道明らけく 治め給える 御代尊。
新嘗祭 11月23日

新嘗祭は天皇陛下がその年の新穀を聞食されるのにあたり、まず天照大御神を始め天神地祇に御親ら新穀をお供えになる祭儀です。全国の神社でもこれにならって御神前に新穀を奉る新嘗祭がおこなわれ、下鴨神社では午前9時から特に本殿の御扉をお開き申し上げて祭儀をおこないます。宮中の新嘗祭は23日午後6時から8時までの「夕の儀」と、午後11時から24日午前1時までの「暁の儀」の2度にわたっての祭儀がおこなわれます。皇居内の神嘉殿において「夕の儀」では夕食を「暁の儀」では朝食を天皇陛下御手ずから神々にお取り分けになり食事を共にされ、私ども国民の平安をお祈り下さいます。23日は戦前「新嘗祭」という祭日でしたが、戦後は「勤労感謝の日」と改称され休日の一つとなってその意義も忘れられてしまいました。私達が夕食をしている頃に天皇陛下は神々と夕食をともにされ、そして私達が寝静まる頃には再び神々と朝食を共にしておられます。暖房の設備もない神嘉殿において、尊き御身ながら2時間もの長い時間を正座の御姿勢をおとりになりお祀りを遊ばします御姿は誠に恐れ多いことであります。昔御所が京都あった頃には京都の人は新嘗祭の日は一日中家で慎み、宮中での神事が終わるまで寝床に入らなかったといいます。私達も先人にならい11月23日新嘗祭は心静かに過ごしたいものです。
お火焚祭 11月下旬

お火焚祭は11月を中心に京都の各神社で盛んに行われている神事です。神前において火を焚き上げ祝詞や神楽を奏して神意をお慰めします。秋の収穫感謝のお祭であるとか、火を焚いて大地を暖め春の息吹を祈るなどお祭りの起源には諸説があります。お火焚祭は民間で行われ、特に鍛冶屋や風呂屋など火を用いる業種ではお火焚の日が決まっている場合があります。お供えには、宝珠の玉の焼印を捺した紅白のお饅頭と新米で作ったおこし、ミカンを供えます。ミカンは焚き火の残り火で焼き、それを食べるとかぜをひかないと言われています。出雲井於神社は通称「柊社」と呼ばれ下鴨の土地の土着の神様で当日は地域の方々が多くおこしくださいます。
御薬酒神事 12月12日

御薬酒神事は創始不詳の古い神事で平安京遷都後は宮中の典薬頭(てんやくのかみ)(皇室の医薬を司る典薬寮(てんやくりょう)の長官)から「白散・度嶂散」(おとその一種)が奉納され、これを以て御薬酒を調製して当神社より宮中に献上すると共に、元旦に当神社の御神前に奉献して国民の安泰と五穀豊穣を祈願した。これが明治初年の祭儀改正以降は一社の秘祭として斎行され、今日に至っている。 若水神事は、元旦の寅ノ刻(午前四時)、新年最初の陽気が兆し始める夜明け前に初春の若水を汲み上げて神前に供えする神事である。しかし、この市中の料理屋さんには、正月料理に用いるため暮れの12月23日ごろ汲み上げ神事を行ってきた。そこで12月13日の事始めに合わせて斎行する事となっている。 神職や参列者一同が斎場である大炊殿(重要文化財、神様の台所)前庭に揃い、御井より汲み上げた清水の前で神事を行い、続いて大炊殿内にて御薬酒の神事を斎行する。 また、この日より社頭にて御薬酒が一般に授与される。
月次祭 毎月一日

下鴨神社におきましては毎月1日に月次奉幣祭並びに月次祭を奉仕致しております。このお祭りは月の始まりにあたり賀茂御祖皇大御神に皇室の弥栄と国家国民の平安をお祈り申し上げるためのお祭りで、これは毎日の御日供(お食事)を一層丁寧にしたものです。