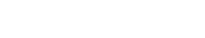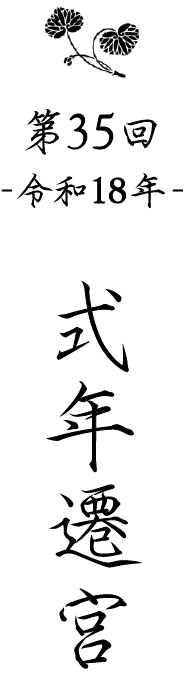
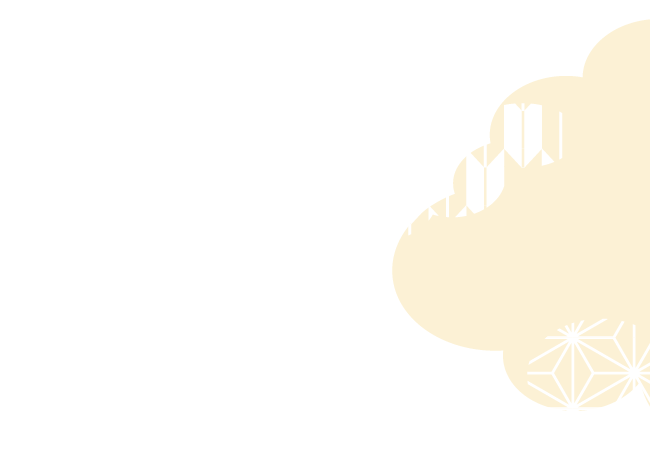
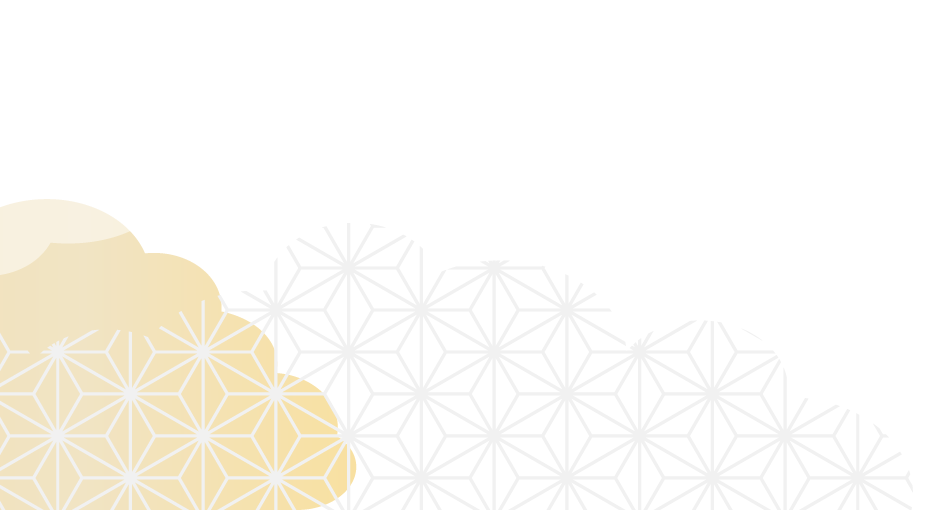
式年遷宮とは
式年遷宮とは、一定年限(定められた年)で社殿を造り替え、遷宮(お宮を遷す)することです。 賀茂御祖神社は本殿2棟は国宝、社殿53棟は重要文化財といずれも日本の宝として登録されており、全てを新しくすることができませんので、お屋根の葺替・金具の修理・漆の塗り替えなどの修理を基本方針としております。

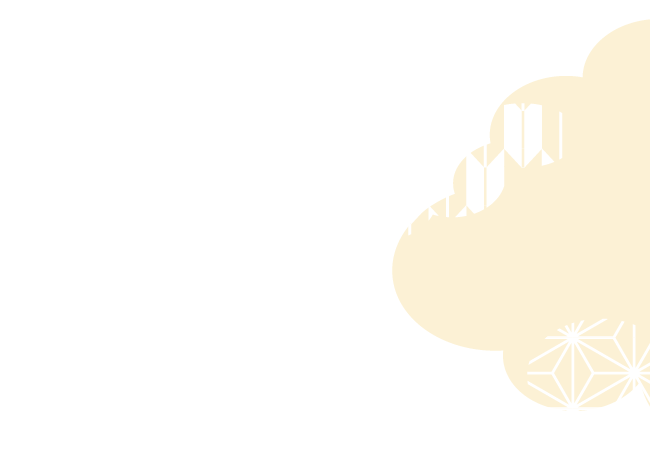
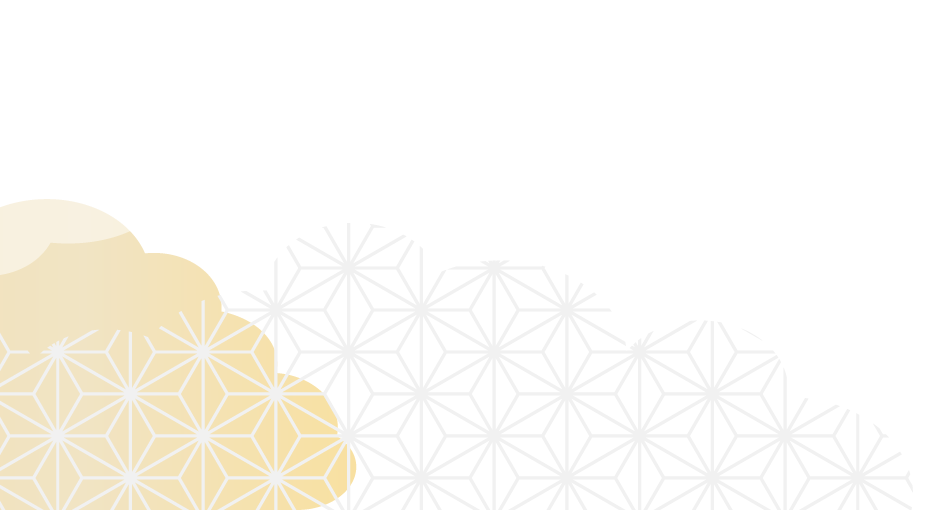
なぜ遷宮するのか
日本の神社には古来より「新しいことを尊ぶ」思想があり、鴨神道独自の信仰として賀茂御祖神社には「御生(みあれ)」の思想が伝承されています。 全ての事象が盛衰を繰り返し、四季の移り変わりや朝晩の明け暮れの中で、あらゆる生命を生み出す力が「御生」です。「御生」は、常に新しい生命力によって力強く清らかであることを意味し、その思想においては社殿の老朽化は穢れを意味します。 式年遷宮はそれらを新しくすることで神の生命力を活性化する重要な祭儀なのです。


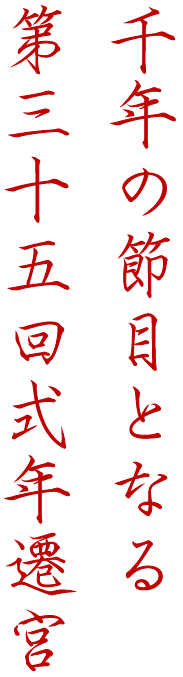
賀茂御祖神社では21年ごとに遷宮を行います。 その始まりは、平安時代長元9年(1036年)後一条天皇の御宣旨により第1回として式年遷宮の制度が確立しました。 「鴨社正遷宮也、当社廿年一度…定例也」と史書『百錬抄』に記されています通り、最初は20年に一度でしたが、今日まで戦乱や飢饉・災害によって30年、50年に及ぶこともありました。現代と時代は変わろうとも、国難を乗り越え常に支障なきよう社殿はお守りされ、今日では21年に一度の制度になりました。 令和18年(2036年)の第35回式年遷宮は、後一条天皇の御宣旨より1,000年の節目にあたる大切な祭儀になります。
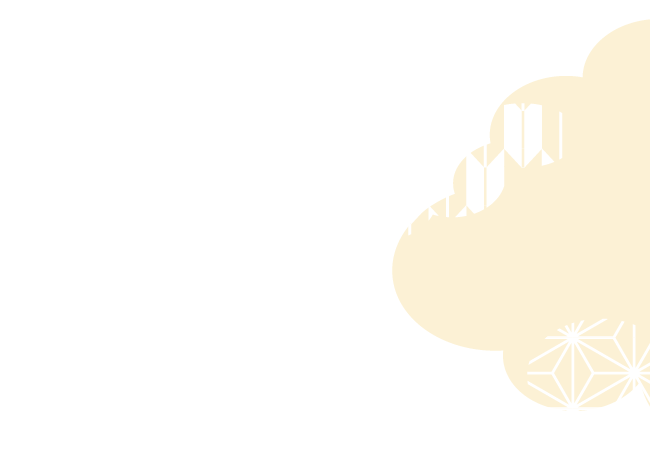
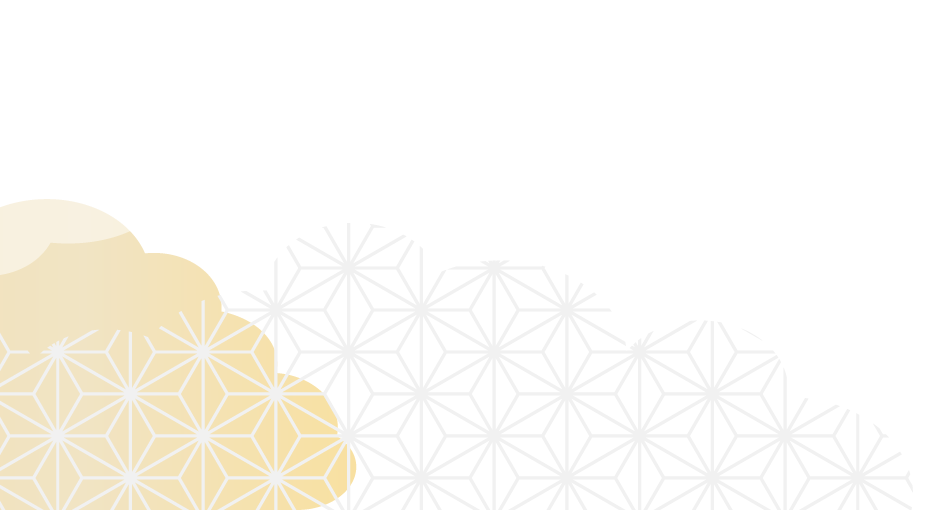
式年遷宮継続事業が
始まりました
今度の第三十五回は、遷宮制度が崇神天皇七年(紀元前九十年頃)、に始められて二千百二十六年目。通算六十回目となります。そして、平安時代、後一条天皇から長元九年(一〇三六)四月十三日に式年制度の宣旨を賜って丁度、一千年目となります。したがって通算第三十五回目の御遷宮をお勤めすることとなります。
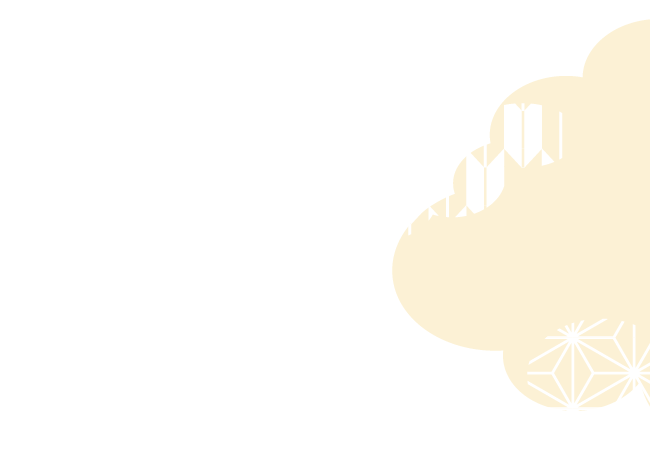
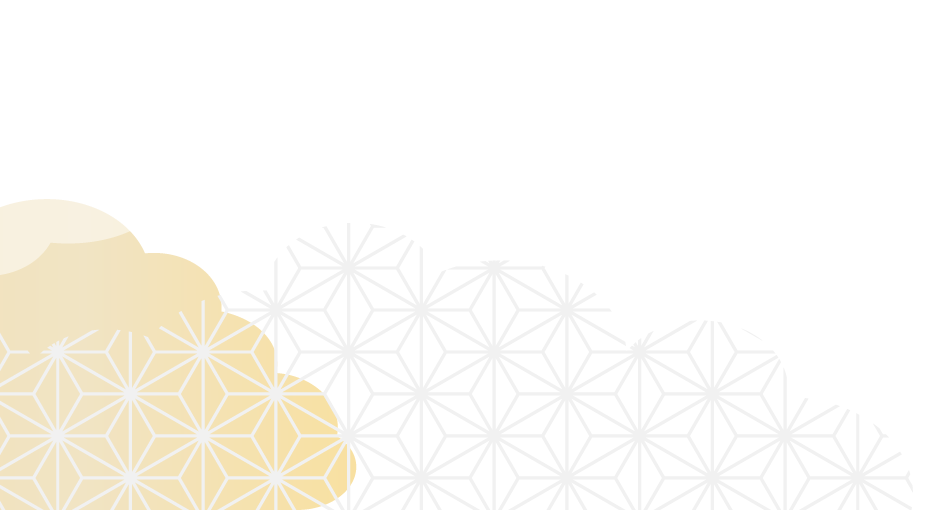
主な内容

国宝の本殿2棟・重要文化財の社殿53棟の修理

ご装束・ご調度等ご神宝類の新調または修理