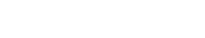葵祭の斎王さまの例祭
- 下鴨神社
- 1 日前
- 読了時間: 2分
七月は、祇園さん一色ですが、四日は、賀茂の斎王さまのお祭の日です。
平安時代のはじめ、弘仁元年四月(八一〇)、賀茂斎王の制度が設けられ、初代斎王として嵯峨天皇の皇女有智子(うちこ)内親王とお定めになられました。斎院庁も設定されました。
平安時代の仁平元年(一一五一)七月四日、賀茂斎院御所の御庭の池の中嶋に祭祀されていた歴代斎王御神霊堂を鳥羽上皇がお祭されたことが『百練抄』などの史料にみえます。今日、新暦の七月四日を例祭日としてお祭を続けています。
この日の御供は、アワかゆとおばなのお餅。(アワは、石器時代の人々の主食で米飯よりアワやヒエが主食であったことから古代祭祀のお祭の祝飯とした遺制です。お粥は、今日の炊飯のことです。御飯とメニューにあれば炊飯を更に水にさらし蒸した強飯のことです。)
尾花は、秋の七草の一つスズキのことです。これも薬草の一種。花の咲く直前の種の部分を炒り、粉に曳き餅に混ぜると言う手間いりのため今日では、黒ゴマを用いています。
御菜は、鴨川のゴリと同じく鮎を干したもの。
献花は、夏椿(お釈迦様さまのシャラの木がわが国には無いのでこの木をなぞらえているとのことです。) それと、秋の七草のおみなえし。
献茶には、境内社、柊社神前の御茶の木の初摘みを御献茶に用いています。
御菓子は、瀬見の小川(『方丈記』の鴨長明にあやかり大正三年の式年遷宮のおりに再現されました。) と、いう古代菓子を用い、古代の祭祀を残します。